学生起業とは?メリット・デメリット、起業の方法、成功するポイントを解説
公開日 2023.12.15 更新日 2024.04.12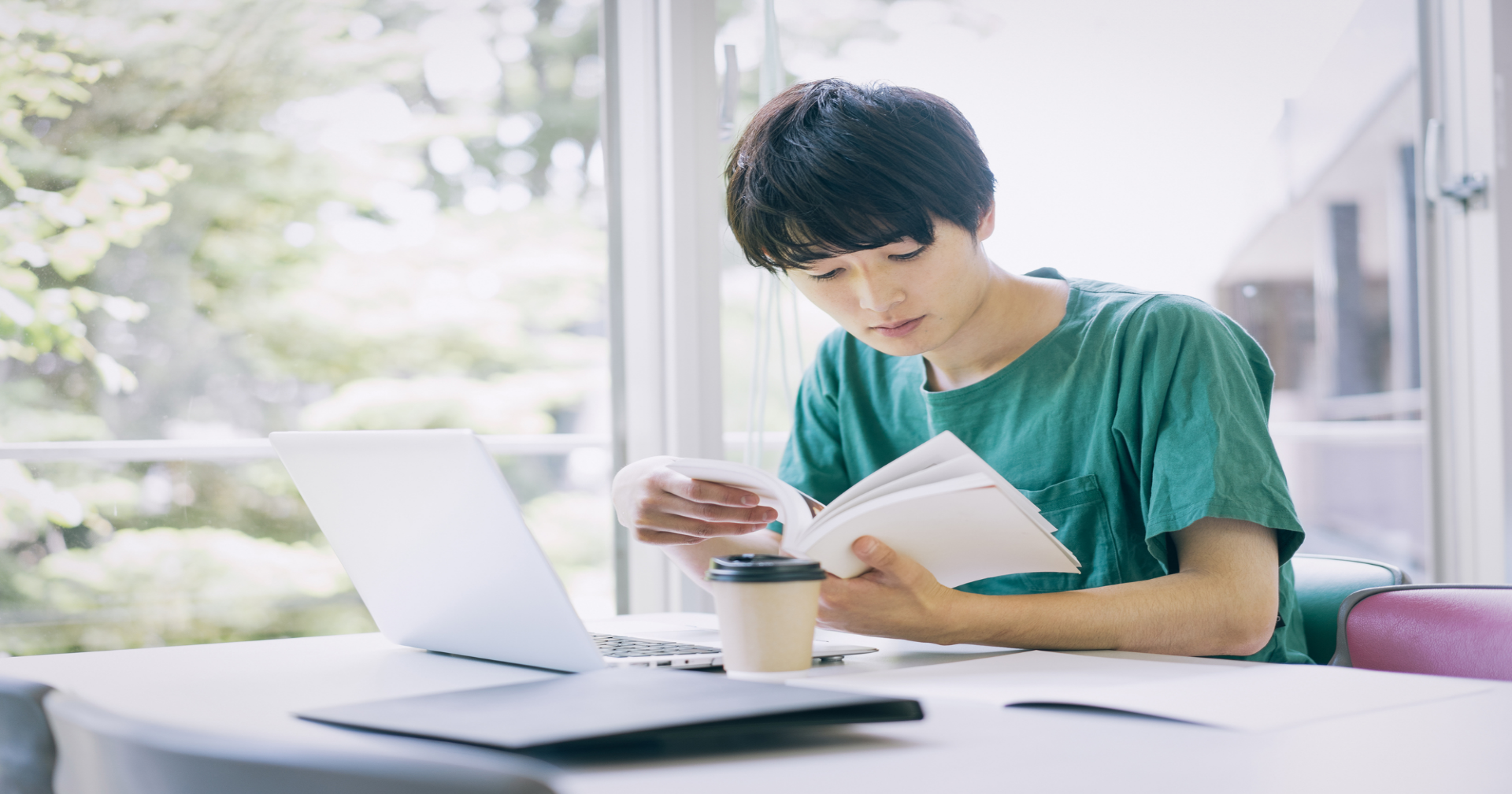
- レンタルオフィス・サービスオフィスのH¹O
- コラム
- 学生起業とは?メリット・デメリット、起業の方法、成功するポイントを解説
近年では、高校や大学に通いながら起業する学生が増加傾向にあるといわれています。実際に学生起業で成功し、知名度の高いサービスを生み出したケースもあるようです。
しかし、いざ自分が学生のうちに起業してみたいと思っても具体的にどう進めたらよいのか、資金調達はできるのか、本当に成功するのかなど、気になる点はいろいろとあるでしょう。
本記事では、学生起業のメリットやデメリット、起業の方法や成功のポイントなどをご紹介します。起業に関心がある学生の方々はぜひ参考にしてください。
<目次>
■学生起業とは?
学生起業とは、文字どおり学生が事業を起こすことをいうのが一般的です。ここ数年では、高校生や大学生が起業するケースも増えており、若手経営者として新聞やメディアで取り上げられているのを見たことがある方もいることでしょう。
起業に踏み切る学生が増えている背景には、「自分の好きな分野で仕事がしたい」「独自のアイデアを形にしたい」「会社員になるよりも個人事業主・経営者になって成功したい」「大学での研究で身に付けた開発技術・経験を活かしてビジネスを興したい」といった思いを持つ人が増加傾向にあることが考えられます。
中でも学生起業で特に見受けられる分野には、Webメディア運営やゲームソフト開発などのIT系ベンチャーが挙げられます。基本的にパソコン一台あれば、さほどコストを掛けずに起業できるビジネスが現れていることも魅力の一つとなっているのでしょう。
■学生起業のメリットは?
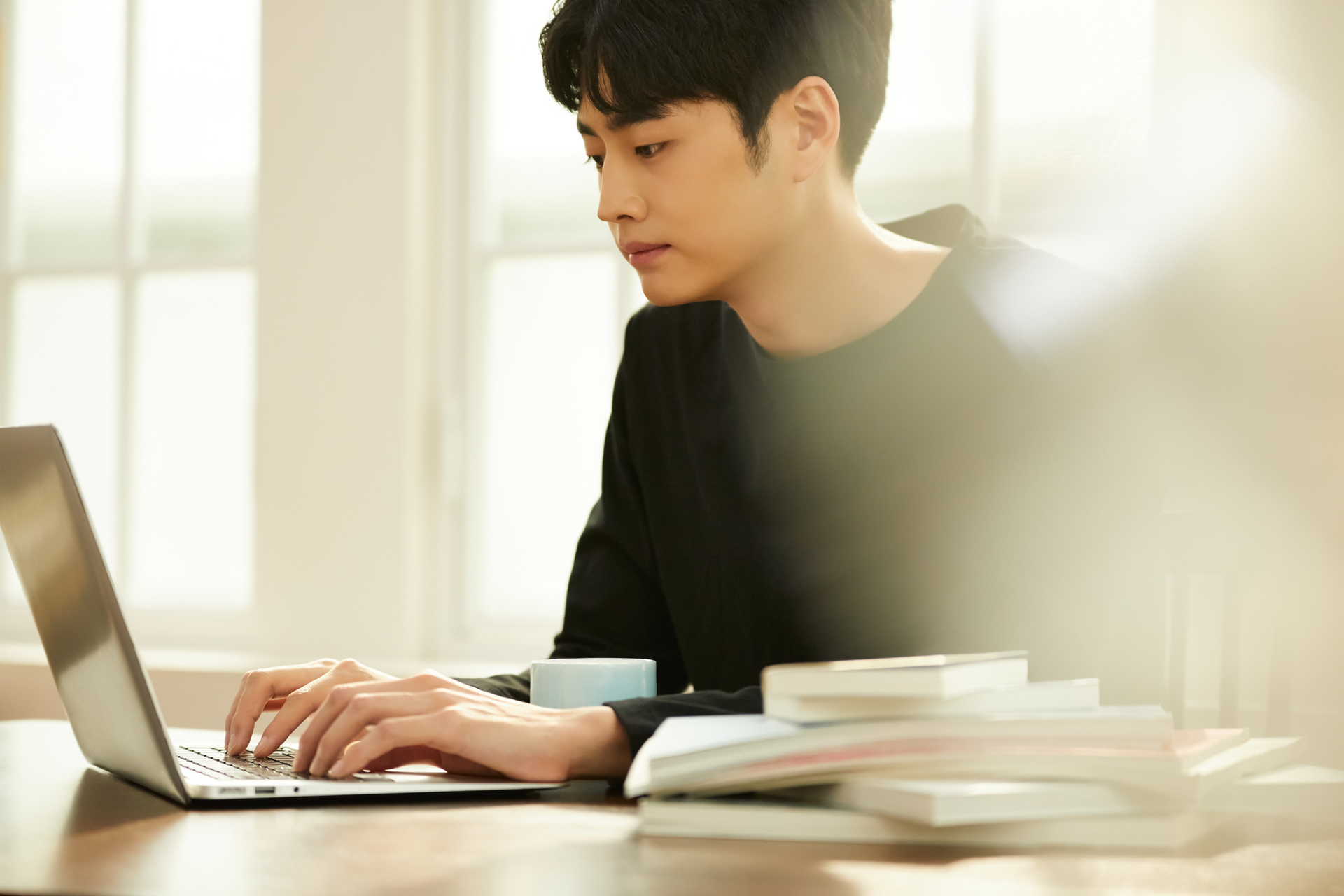
学生起業には、社会人になってからの起業とは異なる、学生時代ならではのメリットがあると捉えられます。具体的にどのような内容のメリットがあるのか、5つのポイントに分けて見ていきましょう。
●学校を拠点としやすい
学生起業の場合、在籍している大学の校舎を拠点として利用しやすいというメリットが考えられます。
大学であれば教室や実験室などの一角を作業スペースやオフィスとして利用できる上、机やイス、照明、電源、コピー機などの備え付けの設備にも不便はしないでしょう。学校によっては、パソコンルームなどに備え付けられたパソコンを使える可能性もあります。
そのため、社会人の起業と比較すると、初期費用やランニングコストは大幅に低く抑えられる環境にあるとみてよいでしょう。
また、大学から許可さえ取り付けられれば、構内でテストマーケティングやアンケートなどを実施する機会も得られるはずです。特に学生や若者をターゲットとしたサービスなどのビジネスを興す場合は、生の声やデータを収集しやすいため、理想的な環境といえます。
●失敗してもダメージが少ない
学生起業では、たとえ失敗したとしてもダメージが少ないのもメリットの一つとなり得ます。
社会人での起業の場合、ビジネスが軌道に乗るまで起業前と比べて収入が減ってしまうリスクがあり、自分が扶養している家族がいる場合は彼らに経済的な苦労を掛ける心配があります。そのため、万が一失敗した際に被るダメージは決して小さなものではないでしょう。
一方で学生は勉強が本業のため、起業していない状態でも収入は短時間のアルバイトなどに頼るケースが多く、社会人と比べて額が少ない傾向にあるといえます。独身の割合も高いため、たとえ起業に失敗しても家族に与えるダメージは小さいはずです。年齢が若ければ若いほど、起業の失敗で得た経験を後の就職活動に活かすことも可能でしょう。
これらの点から、社会人の立場と比べると、失敗したときのダメージが比較的少なくて済む場合が多いと考えられます。
●経験や人脈を築ける
学生時代の起業では、経営や人脈の構築、戦略設計などさまざまな経験を積めることも大きなメリットとなるでしょう。
起業というプロセスでは、サービスを考える、法人設立に向けて手続きをする、事業計画書を作る、資金調達を行うなどビジネスに関するさまざまな経験を積むことができるはずです。
また、若い世代の育成に熱心な年長の経営者や投資家など、起業を通じて多くの人々との間に人脈を築くこともできるでしょう。ビジネスや経営のノウハウを教えてもらったり、融資を受けたりといったサポートが得られる可能性も高いです。
こうしたビジネス経験や人脈は、一般的な大学生活や通常のアルバイトでは得難いものとなると考えられます。
●大学との連携・支援制度の活用ができる
学生起業の場合、大学との連携・支援制度を活用できる可能性がある点も魅力的です。
近年では起業の成功や新ビジネスの育成、事業成長などを支援する目的で、インキュベーション施設を設置する大学が増加傾向にあります。大学によっては、起業に必要な法務や税務、会計などの実務を指導してくれる専門家の紹介や、オフィススペースの提供などのサポートが受けられることもあるようです。
大学での研究成果をベースにビジネスを興した場合、大学側のサポートを受けられる可能性があります。2021年時点で、大学発のベンチャー起業は日本国内に3,000社以上あるとのことです。
こうした大学の支援制度をうまく活用すれば、労力やコストを可能な限り抑えながら起業できるため、よりスムーズな立ち上げと事業展開が見込めるでしょう。
※参考:経済産業省 「大学発ベンチャーの実態等に関する調査」
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/reiwa3_vc_cyousakekka_houkokusyo.pdf,(2022-10-28)
●時間・体力に余裕がある
時間や体力に余裕がある人が多いことも、学生起業ならではのメリットといえます。
そもそも起業には、ある程度の時間とエネルギーが必要とされます。大学生は人生のステージの中で考えると自由に使える時間が比較的多い傾向にあることから、まとまった時間とパワーを集中的に起業へ費やせる人も多いでしょう。勢いに乗ればスピーディーに事業展開へとつなげられる可能性があります。
■学生で起業するデメリットはある?
ここまでのところ、学生のうちの起業にはメリットが多いように見えますが、デメリットもあると考えられます。学生起業にありがちな具体的なデメリットを、2つの観点でご紹介します。
●資金の準備が大変
学生の場合、起業に必要な資金の準備が難しい可能性が懸念されます。
初期費用が必要なビジネスを始めるには、ある程度の元手が必要です。
しかし、学生のうちは自己資金がゼロ、あるいは少ない状況の方が多い傾向にあります。アルバイトをして必要な資金を稼ぐにも、限界があるでしょう。
かといって資金調達をしようにも、学生は信用力が低いとみなされることが多く、金融機関から融資を受けるのは簡単ではありません。
学生に限った話ではありませんが、資金の準備が難しい場合は、なるべく初期投資が少なくて済むビジネスにチャレンジするのがおすすめです。同時に、資金調達に関してもアンテナを張り、いろいろなチャンスを活用しましょう。
例えばクラウドファンディングであれば、実績がない状態からでも、夢やビジョン、活動内容に共感してくれた個人から資金を募ることが可能です。ビジネスコンテストに参加して、自分のビジネスアイデア・ビジネスプランをアピールし、入賞賞金を獲得するという方法もあるでしょう。
●起業と学業を両立する必要がある
起業には膨大な時間とエネルギーを費やす必要がある半面、学生のうちは学業にも力を入れることも求められるはずです。学業よりも起業を優先する学生起業家は少なくないですが、家族から学費のサポートを受けている場合は、彼らからの反対を受ける可能性もあります。
学業より起業を優先したからといって、100%成功するという保証はありません 。そのため、将来の道には就職という選択も視野に入れつつ、起業に取り組むのが望ましいといえます。たとえ困難であっても、学業にもある程度の時間と労力を割きましょう。
また、学生起業は2つのことを両立させなければならない分、友達と過ごす時間も減ってしまうかもしれません。信頼できる友達であれば「一緒にビジネスをやろう」と声を掛ける手もあります。ただし、相手が自分と同じ熱意で取り組んでくれるとは限らず、かえって友情にヒビが入る可能性もあるため、友人と起業する場合は慎重に検討する必要があるでしょう。
■学生起業のやり方・手順
学生起業への思いや熱意があっても、ノウハウがなければ、起業をどのように進めるか分からず苦労する可能性があります。起業を決意する前に、ある程度の流れをつかんでおくとよいでしょう。
ここでは学生起業を目指す方に向けて、実際にはどのようなやり方や手順があるかをご紹介します。
●起業の目的を明確にする
まずは何のために起業するのか、なぜ学生でありながら起業する必要があるのかなど、起業の目的を明確にすることが大切といえます。起業の目的が明確であれば、たとえ道のりが困難でも、また途中で失敗したとしても、高いモチベーションを維持して取り組み続けることができるでしょう。
「自分のアイデアをビジネスとして形にしたい」「お金持ちになりたい」「会社員として組織に縛られず自由に生きたい」など、自分が起業を通じて実現したい目的を具体的に挙げてみるのがおすすめです。また、目的を実現するために起業という手段が本当に最適なのか、必要なことなのかも吟味しましょう。
先述の通り、起業にある程度の時間とエネルギーが必要であり、必ず成功するという保証もありません。他の方法で目的を実現できる可能性もあるならば、リスクの高い起業という選択肢を避けるのもよいでしょう。
起業で何が得られるかだけでなく、起業後に自分がどうなっていたいのか、将来的なセルフイメージを念頭に置きながら、継続的にビジネスに取り組める熱意やエネルギーが自身の中にあるかをどうかよく検討しておくのがおすすめです。
●起業する時期を事前に決める
起業を準備する際には、いつから事業を始めたいか、いつまでに結果を出したいか、あらかじめ起業する時期と期限を定めておくとよいでしょう。
期限が決まっていれば、そこから逆算して起業に必要なステップを具体的に描き出すことが可能です。逆算していけば、各ステップでいつまでに何を揃えておくべきか、何を終わらせておくべきかなど、やるべきこととそれぞれの期限がある程度見えてくるでしょう。
起業の時期や期限が明確化されていないと、結果を出せる見込みもないまま、起業がただ漫然としたマイペースな取り組みになる恐れがあります。目的意識とモチベーションを維持するためにも、スケジュールをしっかりと立てましょう。
●起業して取り組む事業を考える
次に、起業して取り組む事業を考えましょう。自分がどのようなビジネスを展開したいのか、具体的な内容を描くことをおすすめします。
ただし、自分にとってはいかに優れた事業やよいサービスに思えたとしても、実際には実現可能性が低かったり、利益を生み出せず事業としては成立しなかったりするケースもあるでしょう。
そのためこの段階で、書籍やWebの情報などを参考に自分が関心のある分野での既存の事業やサービスについてリサーチし、それぞれの強み・弱みなどを分析するとよいと考えられます。ビジネスのポイントが明確になることで、起業のアイデアをより具体的に描くことに役立てられるはずです。
起業のアイデアが浮かんだら、収益化が可能かどうか、成功が見込めるかなどを検証しつつ、より具体的な事業内容へと落とし込んでいきましょう。
●起業の手続きを行う
具体的な起業のアイデアが固まったら、ここで初めて起業の手続きへと進むのが一般的です。
起業の手続きについて、詳しい内容は次の項でご紹介します。
■学生起業するために必要な手続きや書類
学生起業をするには個人事業主になる方法と法人を設立する2つの方法があり、事業開始の手続きはそれぞれ異なる内容が定められているようです。
株式会社を設立するには、個人事業主になるよりも少し複雑な手続きが必要とされています。また手続きの実費として、少なくとも20万円ほどの費用が掛かるでしょう。
株式会社設立のために費用の準備が難しい場合は、まず個人事業主として開業した上で必要な資金を貯め、「法人成り」を目指すのも一つの方法といえます。法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社といった法人を設立し、事業を法人に変更することを指すのが一般的です。
●個人事業主になる方法
個人事業主は、会社員や法人にはない、いくつかのメリットが考えられます。
会社員は受け取る給与の金額や仕事内容があらかじめ取り決められている働き方ですが、個人事業主の場合は、自分で営業して仕事を獲得する必要があるものの、自分で好きな仕事・案件を選べる自由があります。こなした案件の数だけ報酬が得られるため、頑張り次第で収入を増やせるでしょう。
また、法人よりも個人事業主の方が会計や税務などの処理に関して容易な部分が多い他、青色申告を申請して特別控除を受けることもメリットとして挙げられます。
以下では、個人事業主になる上で必要な手続きについてご紹介します。
・税務署へ開業届を提出する
個人事業主になるには、まず所轄の税務署へ開業届を提出します。開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、所轄の税務署で配布している他、国税庁のホームページからダウンロードして入手することも可能です。
開業届は、原則として事業開始日から1ヵ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。納税地や税務署名、提出日、氏名、生年月日、職業、屋号、事業内容などの必要事項を記載し、漏れがないかきちんと確認した上で提出しましょう。
開業届は提出し忘れたとしても特に罰則の対象にはならないものの、別の手続きを進める上で必要になる場合もあります。提出の前にコピーを作成して、手元に置いておくのがおすすめです。
参考:国税庁 「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm,(2023-10-28)
・青色申告をしたい場合は青色申告承認申請書の提出も必要
青色申告特別控除を受けたい場合は、開業届に合わせて、所轄の税務署への青色申告承認申請書の提出が必要とされています。青色申告特別控除では、最大65万円の控除を受けられるため、節税効果が期待できます。
青色申告の提出期限は、基本的に申告する年の3月15日までとなっています。1月16日以降に新規開業した場合、事業開始日から2ヵ月以内に提出する必要があります。青色申告特別控除を受けるには、複式簿記により記帳した帳簿に加え、賃借対照表と損益計算書も準備しておきましょう。
※参考:国税庁 「A1-9 所得税の青色申告承認申請手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm ,(2023-10-28)
・その他に必要な届出の提出
開業届や青色申告控除申請書の他に、場合によっては別の届出が必要になる場合もあるでしょう。
例えば、配偶者や親族に支払った給与を必要経費として上げる場合は、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」とよばれる書類の提出が必要とされています。青色申告者と生計をともにする配偶者あるいは親族で、その年の12月31日時点で15歳以上となる場合は、この届出の提出が求められるようです。
また、上記の配偶者や親族である青色事業専従者も含め、初めて従業員を雇用して給与を支払う際は、従業員を雇用してから1ヵ月以内に、所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の提出も必要とされています。
以上のように、個人事業主になるにあたりどういった届出が必要になるかは、それぞれの状況で変わるため、事前にしっかりと調べておきましょう。
※参考:国税庁 「A1-13 青色事業専従者給与に関する届出手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm,(2023-10-28)
※参考:国税庁 「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm ,(2023-10-28)
●法人を設立する方法
法人を設立すると登記情報が公開されるなど法人としての責任が発生する一方で、社会的な信用が得られ、資金調達も進めやすくなるでしょう。法人税の対象となるため、収益が増えるほど高い節税効果も期待できます。
法人設立の具体的な進め方は、以下でポイント別に詳しくご紹介します。
参考:財務省 「法人課税に関する基本的な資料」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c01.htm,(2023-10-28)
・公証人役場で定款認証を受ける
株式会社などの法人の設立を行うには、正式な手続きに沿って、公証証人による認証を受ける必要があるとされています。定款認証は公証人役場で受けますが、会社が所在する地域の法務局で手続きを行うのが一般的です。
定款とは、会社運営のルールをまとめたものを指すとされています。定款には設立日や商号、事業目的、会計年度、本店所在地、役員の構成、発起人の氏名・住所など細々した項目の記載が必要になるため、作成にはそれなりの時間が必要となるでしょう。
定款認証の後に必要とされているのが、法務局で法人の設立登記です。設立登記によって、会社の基本情報が法務局に登録されて公的に認められた団体となり、今後の事業活動をスタートできる仕組みとなっています。なお、2023年10月現在、設立登記の方法はオンラインで行うことが推奨されています。
※参考:e-GOV 「公証人法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=141AC0000000053 ,(2023-10-28)
法務省 「一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00117.html,(2023-10-28)
・資金を払い込む
定款が認証された後は、出資金を払い込みましょう。出資金は設立する会社で事業を始めるにあたり必要となる資本を指します。貯蓄や株式などの自己資金を用いる、あるいは金融機関から借り入れるなどして調達する方法があります。
この時点ではまだ会社の銀行口座は開設できないため、出資金の払い込み先は、発起人の個人口座とするケースがほとんどです。出資金には特に下限がなく、1円からでも申請が可能です。さほどコストの掛からない事業を立ち上げる場合は、資本金が少額でも会社設立に支障はないでしょう。ただし、あまりにも資本金が少ないと、事務所の設置や備品の購入などに必要な資金が不足する恐れがあるため、注意が必要です。
自分で一から事業を興す際、特に学生起業の場合は、資本金は自己資金で賄われるのが一般的とされています。
・登記申請書類の作成・法務局で申請
次に登記申請書類を作成して、法務局で登記申請を行いましょう。登記申請は代表者が行うものですが、委任状を提出することで司法書士などの代理人が代行することも可能です。
登記申請には、設立登記申請書、定款、発起人の同意書、設立時代表取締役の就任承諾書、監査役の就任承諾書、発起人の印鑑証明書、資本金の払込書を証明する書面、印鑑届出書など、さまざまな書類が必要となります。
また、税務署への法人設立届出書類の作成と、所轄の税務署への提出も必要です。会社という法人を設立すると、国や自治体に税金を納める義務が生じるため、必ず手続きを行いましょう。
税務署での法人設立手続きに必要な書類は、国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署に問い合わせれば入手できます。
※参考:法務局 「商業・法人登記の申請書様式」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html,(2023-10-28)
■学生起業を成功させるポイント

たとえ学生であっても、起業するからには事業を軌道に乗せて成功を目指す人がほとんどでしょう。学生起業で失敗しないために意識するべきポイントについて、それぞれ詳しくご紹介します。
●事業計画を立てておく
まずは、事業計画をしっかり立てましょう。どんなによいアイデアでも、具体的なプランが欠けていれば実現可能性が低いと見なされる可能性があります。事業計画書とは、事業をどのように行うかの具体的な計画であり、事業内容や顧客層、戦略、見込まれる売上・収益などをまとめたものを指すのが一般的です。
事業計画書は、金融機関に提出して事業内容を納得させて融資を引き出したり、会社設立に関わるチームや関係者に具体的な事業内容を共有して協力を得たりする場合に必要とされる書類といえます。
事業計画を立てる上で役に立つ考え方に「6W2H」というものがあります。「Why(事業を行う目的)」「What(展開するサービスや商品内容)」「Where(事業を展開するエリア・市場)」「Whom(ターゲットとなる顧客)」「When(事業の開始時期)」「Who(必要となる人材)」「How Much(必要となる資金や見込まれる利益)」「How To(商品・サービスを売るのに必要なもの)」といったポイントを押さえておくと、必要な事項を漏れなく事業計画の内容に盛り込めるでしょう。
●スモールスタートを意識する
スモールスタートを意識するのも、学生起業を成功に導く上で役立つポイントといえます。スモールスタートとは、まずは小規模で物事を始めるという意味で使われている言葉を指すのが一般的です。スモールスタートにすることで、起業の準備に掛かる時間や手間を小さく抑えられるため、学業と両立させながら取り組みやすくなるでしょう。
企業は事業規模が大きいほど失敗したときに被るダメージは甚大なものとなりますが、反対にいえばスモールスタートは、たとえ失敗しても被るダメージが比較的小さくなります。また市場や経済情勢、消費者のニーズに起こる変化などに対しても、事業の軌道修正がしやすい傾向にあるといえます。
なお、起業の際には 最初は一人でスタートするのがおすすめです。仲間を集めて作業負担を分散するのも一つの方法ですが、全員が同じレベルの熱意やモチベーションで取り組めるとは限らないです。内部分裂のリスクを回避するためにもまずは自分一人でスタートし、事業が軌道に乗ってきたら信頼できる仲間を誘うのがよいでしょう。
●学生を対象としたサービスを考える
学生起業家が事業内容を決める際には、学生を対象にしたサービスにすると進めやすいでしょう。学生企業の拠点は多くの場合大学内にあり、身近に学生が多い環境といえます。学生向けのサービス展開を目指すにあたって、ターゲットとなる顧客層に常に囲まれている環境は有利となるでしょう。
利用できる場合は、アンケート調査やテストマーケティングを実施し、手軽にデータ収集することも可能です。収集したデータは、サービス対象のユーザー分析やマーケティング戦略の立案などに役立てられるはずです。
同年代の学生であれば、それぞれの置かれた立場や心情、ニーズ、課題感なども把握しやすく、どのようなサービスなら相手に刺さるかのイメージをしやすいでしょう。結果として、展開するサービスの成功率を高める効果が期待できます。
●インターンシップ・ビジネスコンテストなどに参加する
企業が募集しているインターンシップや実施しているビジネスコンテストなどに参加するのも、学生起業の成功率を高める上で有効な手段といえます。
インターンシップでは、その企業の経営陣や社員、他の学生との出会いを通じて、新たなアイデアや知見を得られるでしょう。実際の企業での業務を通じて、ビジネスの動きや会社経営・運営の流れを体験するにもよい環境といえます。これまでにない人生経験を積んだり、ビジネススキルを高めたりするなど、多くのメリットが期待できます。
ビジネスコンテストでは他大学のチームも参加するため、新しい発想や着眼点を得られる可能性があります。審査員である経営者などから、自己のプランやアイデアの改善点などをアドバイスしてもらえることもあり、経営計画をよりよいものにするために役立てられるでしょう。
■まとめ
学生起業は、大学を拠点にしたり大学と連携したりすることでコストを最小限に抑えられる、失敗してもダメージが少ないなどのメリットがあるとされています。特に若年層・学生向けのサービスを展開していくには恵まれた環境といえるでしょう。
どのような事業を立ち上げるにせよ、拠点となるオフィスは必要となるはずです。場合によっては大学構内を利用することも可能ですが、本格的な起業を考えているならサービスオフィスを活用するのもおすすめです。サービスオフィスでは、入居する企業や個人同士の交流を通じて人脈を広げたり、新たなビジネスチャンスのきっかけがつかめたりするため、事業の発展を目指す人にとっては多数のメリットがあるでしょう。
サービスオフィスの活用を視野に入れている方は、小規模ビジネスに適した環境が整ったH¹Oをご検討ください。スモールスタートで始めたい学生起業にもぴったりの環境といえます。見学や資料請求もできるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。







